業界動向
Access Accepted第522回:2016年の欧米ゲーム業界を振り返る
 |
VR対応ヘッドマウントディスプレイがリリースされ,4000本を超えるPCタイトルが市場に登場し,大手パブリッシャの大作の販売実績が振るわなくなってきた2016年。欧米ゲーム市場にとっては怒濤の1年だったが,それもすでに12月の半ばを過ぎた。というわけで,今週は2016年の「欧米ゲーム業界を振り返る」をやってみたいと思う。
ゲームに満ちた2016年
 |
記事で紹介したタイトルの中には,発売が延期となったり,アーリーアクセスのままで発売されてしまったりしたものもあるが,この1年,筆者を含めて多くのゲーマーが,何をプレイすべきか,タイトル選びには苦労したはずだ。遊びたいゲームが多すぎて,どこから初めていいのか分からないという雰囲気だ。
本連載の第520回「新作ラッシュにあえぐ中小デベロッパ」でも書いたように,2016年は,SteamでリリースされたPCタイトルだけでも4200本を上回り,まさに怒濤の新作ラッシュが繰り広げられた1年でもあったのだ。
市場規模がそれに応じて拡大していれば嬉しいのだが,果たして,どうなのだろうか。いずれ,詳しい数字が調査会社などから発表されるはずだが,既存のゲーマーについて言うなら,登場したゲームを消化できているとは思いづらい。Steamでリリースされた4000本を超える作品のうち,投資を回収して利益を得られたタイトルはいったい,どれほどあったのか疑問だ。
また,今年は「VR元年」でもあった。Oculusの「Rift」とHTCの「Vive」が春に,そしてSony Interactive Entertainmentの「PlayStation VR」が11月にリリースされ,没入感の高い,新たなエンターテイメントの世界が幕を開けた。
もっとも,供給量の不足や高めの価格に対する不満などから,VR市場が本格的にテイクオフしたとは言いづらい。また,VR対応ソフトの売り上げは,「ミリオンセラーなど,夢のまた夢」という現状だが,その割にはリリースされるタイトルが(過去の新ハードの例に比較して)多すぎることは,本連載の第518回「PlayStation VRの売れ行き,データから浮かび上がるVR市場の現状」でも指摘したとおりだ。
AAA+タイトルの台頭で,AAAタイトルはもう売れない?
12月12日に掲載されたgamesindustry.bizの記事によると,ヒットチャートに名を連ねるモバイルゲームは,ほとんどが2015年以前にローンチされたものである。そのため,2016年に登場した新規タイトルは上位作品の厚い壁に阻まれ,トップリストに登り詰めることが難しくなっているという。
これは,欧米のPCゲームにも言えそうで,調べてみると,SteamのDAU(日ごとのアクティブユーザー)の上位に居座り続けているのは「Team Fortress 2」や「Dota 2」など,古くからあるタイトルばかりだ。
Steam以外を見ると,「League of Legends」や「Minecraft」「World of Warcraft」「World of Tanks」,そして「FIFA」シリーズなどの,2016年以前に登場したタイトルが利益を出し続けており,今年はここに「Overwatch」が加わった。一部のゲームにプレイヤーが集中する傾向は昔からあるが,今年はそれがさらに顕著になり,新規作品の大半は埋没しているように思える。
ちなみに,上に並べた人気タイトルは最近,欧米ゲーム業界で「AAA+タイトル」と呼ばれるようになっている。開発費はともかく,広報やバックエンドのサーバー維持に巨額の投資が必要になるので,「AAAタイトル」の1つ上を行く「AAA+タイトル」というわけだ。
共通しているのは,「少なくとも1年,長ければ10年」というスパンでサービスが行われていることで,これはまた,「GaaS」(Game as a Service)型タイトルとも呼ばれる。Free-to-Playやアーリーアクセス,定期的にリリースされるDLCやシーズンパス,そして,ファンメイドMODの受け入れによる顧客の囲い込み戦略など,長期的な展望に立ちつつもスピード感を持ってサービスが行われる作品も,GaaSという枠組みで捉えられているようだ。この流れは,パッケージ販売が主体だったコンシューマ機でも見られ,遠くない将来,メインストリームになるだろう。
つまるところ,昔ながらの売り切り型「AAAタイトル」は,たとえ膨大な開発予算と宣伝費をかけたとしても,売れなくなっているのだ。
 |
ざっと見ると,Activisionの看板タイトルシリーズの最新作「コール オブ デューティ インフィニット・ウォーフェア」のセールスは予想外に低調で,PlayStation 4およびXbox One版を合わせて600万本ほど。日本から見れば十分な数字に思えるかもしれないが,報道によれば,2015年の「コール オブ デューティ ブラックオプスIII」の同時期比で50%以下であるという。
さらに,2016年のAAAタイトルであった「ミラーズエッジ カタリスト」や「Quantum Break」,そして「Gears of War 4」「タイタンフォール 2」「マフィア III」なども,メディアやプレイヤーの評価は総じて高いにも関わらず,期待されたほどのセールスには結びつかず,なかには100万本を売ることさえままならない作品もある。
 |
したがって,AAAタイトルがAAA+タイトルに駆逐されているのは間違いないところだ。読者の中にも筆者と同様,最近のゲームは「長期にわたるサービスである」という実感を抱いている人も多いのではないだろうか。今後の欧米ゲーム業界を考えるとき,この傾向をどう捉えていくべきか? 2017年になれば,もう少し明確な答えが出てくるかもしれない。
以上,2016年の欧米ゲーム市場を概観したが,以下に今年の重要なトピックを5つ,ピックアップして並べてみた。前の文章と重複する部分もあるが,参考にしてほしい。
1.VR対応ヘッドマウントディスプレイが勢揃い
冒頭にも書いたように,2016年はOculusの「Rift」,HTCの「Vive」,そしてSony Interactive Entertainmentの「PlayStation VR」という本格的なVR対応ヘッドマウントディスプレイがついに出揃った。普及台数は必ずしも多くはなく,また,じっくり遊び込めるタイトルも今のところ少ないようだが,VR対応ヘッドマウントディスプレイは未来を感じさせるデバイスでもある。
Oculus VRのチーフサイエンティスト,マイケル・アブラッシュ(Michael Abrash)氏は講演で「5年後のVR」をかなり具体的に予測しているが(関連記事),これらが本当に実現するのか,今から期待は高まる。
ローンチ後,Riftは3つめのセンサーユニットを使って,Viveの“ルームスケールVR”を実現しており,一方のValveは「Oculus Touch」風のコントローラを新たに開発中であると発表した。ハードウェア的にRiftとViveは近づいているように見えるが,ゲーマーやソフト開発者にとっては,そのほうがありがたい。すでに「PlayStation VR」をPCに接続して,SteamのVRタイトルをプレイすることができるという非公式MODも登場しており,SIEが2017年にどういうアクションを取るのかにも注目したい。
 |
2.買収攻勢に晒されたUbisoft Entertainment
6月に開催されたE3 2016は,ActivisionやElectronic Artsなどの大手パブリッシャがブース出展を見合わせ,いつもとはかなり違う雰囲気だった(関連記事)。筆者はここ数年,Ubisoft EntertainmentがE3で行うプレスカンファレンスのレポートを担当しているが,こちらもまた普段とはムードが異なっていた。
例年なら,Ubisoftの創設者で,30年にわたって同社を率いてきたイヴ・ギルモ(Yves Guillemot)氏が最後にクロージングコメントを述べて終わるのだが,今年は最後に,プレゼンテーションを行ったスタッフが全員が壇上に立ち,同社の結束力を見せるような閉幕となっていたのだ。
この演出には,Ubisoftが現在も晒されている買収攻勢が影響を与えていると思われる。詳しくは本連載の第476回,「Vivendiが仕掛けたUbisoft買収の動き」を参照してほしいが,10月に記事を掲載して以降も,Ubisoftに対するVivendiの敵対的M&Aは続いており,Vivendiは持ち株比率を10%から25%に引き上げている。これは,Ubisoft自身が保持する23%を超える数字だ。
9月の株主総会後にリリースされた「ディビジョン」や「ファークライ プライマル」「ウォッチドッグス 2」といったタイトルは(メガヒットとは呼べないものの)手堅いセールスを記録しており,2017年にも注目のタイトルが並ぶ。皮肉にも,これがVivendiの購買意欲に油を注いだようだ。
Vivendiは今後も買収攻勢を強める姿勢にあり,Gameloftを買収するなど,ゲーム市場への再参入を本気で模索している。2017年は,Ubisoftにとって激動の年になるかもしれない。
 |
3.コンシューマ機の世代交代と4K時代の到来
2016年,「PlayStation 4 Pro」と「Xbox One S」が発売された。PlayStation 4とXbox Oneが次世代機として発売された2013年(PS4は日本では2014年),「寿命は8年から10年」と予測する関係者も少なくなかったが,わずか3年でのモデルチェンジと見ることもできる。確かにPlayStation 4とXbox Oneという“器”の寿命は延びたかも知れないが,今後はモバイル端末と同様,短いスパンでの機種更新が続くかもしれない。
PCと異なり,ハードウェアが固定されていることがゲーム開発における大きなメリットだったはずのコンシューマ機が,PCのような機能強化を繰り返すわけで,いずれ「初代PS4では動かないが,最新型PS4だと遊べる」といったゲームも登場してくるかもしれない。果たして,ユーザーはそれをどう思うだろうか。
積極的に捉えれば,解像度でスマートフォンにさえ遅れをとっていたコンシューマ機が,ようやく4K解像度の時代に突入したことは評価できる。もっとも,Xbox One Sは今のところ映像コンテンツのみのサポートで,4K解像度でゲームをプレイするには,2017年に発売される「Xbox One Scorpio」を待つ必要がある。
2020年の東京オリンピックが近づくにつれ,日本でも4Kテレビが普及し,それに合わせて4K対応ゲームもスタンダードになっていきそうだ。
 |
4.「スーパーマリオラン」や「Nintendo Switch」など,任天堂の新たな展開
2016年7月にローンチされたNianticの「Pokémon GO」が社会現象ともいえるフィーバーを巻き起こしていることは,今さら言うまでもないだろう。任天堂が制作するタイトルではないものの,改めて任天堂の誇るIPの底力を感じさせる出来事だ。「スーパーマリオラン」が登場した今,これほどのIPを持たないほかのモバイルゲームパブリッシャは,戦々恐々としているかもしれない。
任天堂はさらに,次世代コンシューマ機「Nintendo Switch」を2017年3月に発売すると発表した。
性能などについては今のところ未発表だが,据え置き機のようにもモバイル機のようにも使えるというコンセプトが,コアな任天堂ファン以外の支持者をどれだけ得られるのかがポイントになるだろう。
2017年1月13日に予定されている「Nintendo Switch プレゼンテーション 2017」で,Switchの明確なコンセプトとソフトウェアのラインナップ,そして任天堂の今後の方針などが明らかになるはず。来年の任天堂とその周辺は,ここ数年見られなかったほどの活気を帯びてきそうだ。
 |
5.Amazonが無料ゲームエンジン「Lumberyard」で市場参入
ほんの10年前,ゲームエンジンのライセンス料は3000万円ほどしたという。それでも,「エンジン開発のためのプログラマーを多数,数年間にわたって雇うよりも安い」という理由で,ゲーム開発会社は市販のゲームエンジンを使っていた。
Unity Technologiesがコペンハーゲンで産声を上げたのは2004年で,翌2005年,彼らの最初の製品「Unity」の第1版が安価なゲームエンジンとしてリリースされた。そして,同社がアメリカに移った2009年頃から,ゲームエンジンの価格競争が始まり,現在では「Unreal Engine 4」が無償化(開発したゲームの売り上げが一定額を超えると,ロイヤリティが発生),また,「CryENGINE」の最新版「CryEngine V」は,開発者の言い値で販売という形になっている。
こうしたエンジンの価格競争が続く中,ゲーム産業への進出を図るAmazonが,無料のゲームエンジン「Lumberyard」を発表したのだ(関連記事)。
開発ツールの極端な低価格化が,冒頭に述べたゲームの爆発的なリリースにつながっていることは言うまでもないが,Amazonの無料ゲームエンジンはその傾向に拍車をかけることにもなりそうだ。2017年には「Lumberyard」で作られたタイトルも多数,出回ることになるかもしれない。
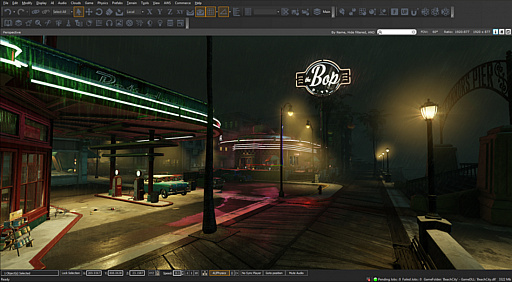 |
冒頭の話に戻ってしまうが,2016年は,多数のタイトルが発売された年として記憶されるはずだ。独立系デベロッパによる,一部のニッチ層に向けて勝負するような作品も増えており,ゲームの裾野が広がった年でもあった。「表現したいものを,ゲームを使って表現する」という作品が出てきたことは,メディアとしての成熟を示すものでもあるだろう。年末を迎えて,そんなことも思った2016年だった。
著者紹介:奥谷海人
4Gamer海外特派員。サンフランシスコ在住のゲームジャーナリストで,本連載「奥谷海人のAccess Accepted」は,2004年の開始以来,4Gamerで最も長く続く連載記事。欧米ゲーム業界に知り合いも多く,またゲームイベントの取材などを通じて,欧米ゲーム業界の“今”をウォッチし続けている。
- この記事のURL:


















