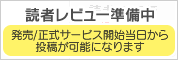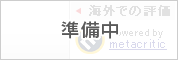「
Nevergrind Online」は,インディーデベロッパのNeverworks Gamesが開発中のタイトルだ。現在はSteamにてアーリーアクセスが行われており,本稿の執筆時点では2050円(税込)の買い切り型として販売されている。
一人称視点でダンジョンを攻略するゲーム画面を見る限り,
「Wizardry」や
「Might & Magic」に代表される,オーソドックスなダンジョンRPGをイメージする読者は多いだろう。しかし実は本作は,最多5名のマルチプレイに対応した
MORPGなのである。これまでありそうでなかった,ユニークな各種システムを紹介しよう。
見た目はダンジョンRPG。でも実は全然違う!?
一般的なダンジョンRPGでは,プレイヤーは5〜6名によるパーティを操作(管理)するが,本作は
プレイヤーキャラ1名に専念することになる。拠点エリアには大勢のプレイヤーキャラがたむろしており,最初はここでパーティを編成する。そして「酒場」を通じてダンジョンへ移動し,そこで待ち受けるボスモンスターを討伐するとクリアだ。これを繰り返して,レベルアップやトレジャーハントに勤しむのが基本的なゲーム展開となる。
拠点エリアでは,画面の右側にプレイヤーキャラの一覧が表示される。これを見ながら近いレベルの人を誘ったり,“誘われ待ち”をしたりと,昔ながらのプロセスでパーティを編成するのだ
 |
レベルごとに用意された各ミッション(ダンジョン)は,それぞれノーマルとヒロイックの2種類の難度が用意されている。大まかに言うと前者はソロプレイまたは少人数向け,後者はフルパーティ向けのゲームバランスだ
 |
ダンジョンはランダム生成で,その内部は複数の部屋(玄室)と,それらを結ぶ通路によって構成される。玄室からは東西南北への通路が延びるが,通路は直線で,ここでの移動は前進・後退のみというシンプルなシステムだ。
本作における移動操作はリーダーに一任されるのだが,このときに判断を要する部分は少ない。たとえばダンジョンRPGのように,トラップを警戒しながら一歩一歩慎重に進む必要はないので,比較的カジュアルに進行できるだろう。
通路ではモンスターが行く手を阻むが,向こうから接近してくることはない。こちらから前進して,シンボルエンカウント形式でバトルへ画面へと切り替わる
 |
玄室ではモンスターが待ち受けているほか,バフを獲得したり宝箱を発見したりすることも。ミニマップに表示されるアイコンで玄室の大まかな種類が分かるので,これを参考に移動する
 |
シンボルエンカウントでモンスターと遭遇すると,各メンバーが自身のプレイヤーキャラ(1名)を操作する形で,
リアルタイムバトルが行われる。オートバトルによる通常攻撃の合間に,クールダウンタイムで管理されたアクティブスキルを繰り出すという,この部分に限っていえばMMORPGライクなシステムとなっている。
昔ながらのMMORPGらしい協力プレイを実現
本作のバトルには
ヘイト(※簡単に説明すると,モンスターの各キャラへの敵対心を数値化したもの)の概念がある。各モンスターの頭上には,現在のヘイト値が最も高い,つまり攻撃対象のプレイヤーキャラのアイコンが示されている。これをリアルタイムで確認しながらの
協力プレイは,本作の大きな醍醐味のひとつだ。
たとえばクルセイダーを初めとしたタンク系のクラスは,ヒーラーを狙っているモンスターを発見したら,ヘイトを高めるスキルで素早く引き剥がさないと,パーティーへの回復が滞ってしまう。また,ウィザードをはじめとするアタッカー職がメテオスウォームのような大技を繰り出すときは,自分にターゲットが向いていないことをあらかじめ確認しておかないと,詠唱直後に袋叩きにされかねない。
本作の各ミッションは,ノーマルモードとヒロイックモードの2種類の難度が用意されているが,レベル20台以降のヒロイックモードでは,
ヘイトコントロールを意識した仲間との協力プレイが求められる。プレイヤーキャラの姿が画面上で視認できないこともあり,現在のターゲットが誰なのかを把握するには多少の慣れが必要だが,ダンジョンRPGの見た目でこういった協力プレイを行うのはとても新鮮だ。
ちなみに,プレイアブルクラスの種類は,タンク,アタッカー,ヒーラー,バッファーに大別されており,それぞれのスキル/スペルの名称も含め,歴史的MMORPG「
EverQuest」からの強い影響を受けている。本作における協力プレイの奥深さは期待していいだろう。
とはいえ,こういった協力プレイが常に求められるわけでもない。非戦闘時にはHPなどがみるみる自然回復し,たとえやられてしまっても戦闘終了後に復帰できる仕様なので,ヒーラー職がいないようなパーティ編成でも,なんとなくのノリで攻略可能だ。さらに言うと,基本的にはパーティプレイ向けのゲームバランスではあるが,ノーマルミッションならほとんどのクラスがソロプレイで攻略でき,奥深さと間口の広さの双方に抜かりがない。
ただ,個人的に気掛かりなのは,ゲームバランス以外でもEverQuestからの影響があまりにも強く見られることである。人によっては懐かしさたっぷりでプレイできるし,そこが本作の大きな魅力の1つとなっているのも事実だが,たとえば多くのSEが
控えめに言って“限りなく似ている”のは,リスペクトやオマージュの範囲をやや逸脱しているようにも思える。
これはfroglokならぬtoadlokという種族のモンスター。こういった,EverQuestの経験者なら反応せずにはいられないネタが,ゲーム内のそこかしこに散らばっている。SEに関しても,筆者などはレベルアップするたびに「DING!」と/shoutしたくなってしまう
 |
荒削りだが,それすらも黎明期のオンラインゲームらしさを感じられる
現在の本作はアーリーアクセス中で,頻繁にアップデートが行われており,いわば進化の過程にある。しかも,7月中旬に本作の日本語対応が行われてから,日本人プレイヤーが急増しているのだ。タウンエリアでは日本語チャットが飛び交うどころか,サーバーダウンも頻発している。完成品を望むプレイヤーに向けては,本作はまだちょっとお勧めできる段階ではない。
本作はシングルプレイ専用のゲームモードもあり,こちらはオフラインでも遊べる。どのクラスもレベル5前後で主要スキルを一通り習得できるので,サーバーダウンのときなどにいろんなクラスに触れておくと,協力プレイ時に生かせるだろう
 |
しかし個人的には,こういったバグの数々やサーバーダウンすら,オンラインゲーム注目作のサービス開始直後における
カオスな状況を想起させられ,たまらなく楽しい。
本作の各種システムがチャレンジングなものであることは,歴戦のゲーマーならすぐに理解してもらえるだろう。そういった可能性を秘めたゲームにいちはやく目を付け,同好の士と共に手探りで攻略しながら,完成に向かって進化する様を見届ける。これは,オンラインゲームにおける最も粋な(?)遊び方だと筆者は考えているが,まさか2022年に再び味わえるとは夢にも思わなかった。
数か月後の本作は,各種システムが確実に進化しつつも,その一方で全プレイヤーが手探りで進める独特の空気感のようなものはスポイルされているかもしれない。攻略サイトだってきっと完全なものが作られていることだろう。現在,オンラインゲームの進化は行き着くところまで行っているだけに,いまの本作における荒削りな面白さは大変レアで,実際に多くの日本人プレイヤーがそのことを口々に語っている。
昔ながらのMMORPGへのリスペクトにあふれるゲームということもあり,日本人プレイヤーが集まるゲーム内ギルドやDiscordでは,オンラインゲームの昔話が語られることも。サーバーダウンの直後にはチャットが滝のように流れ,この雰囲気もまた懐かしい
 |
Nevergrind Onlineは,ヘイトコントロールやトレハンといった面白さのコアな部分を大切にし,それ以外は極限まで削ぎ落としたようなゲームである。ダンジョンRPGに協力プレイを盛り込んだ部分は革新的だが,それ以外の大半の要素は古臭い。ストーリーもあってないようなものだし,オートバトルやオートマッチングなんて便利なシステムもない。どちらかというと全体的に不便だ。だが,それがいい。
黎明期のオンラインゲームに思い入れがある人なら,本作が深く刺さる可能性は高い。もし興味を持ったなら,正式サービス開始を待たずに
いますぐ,本作をプレイしてほしい。
戦闘終了後は,各プレイヤーがどれだけの量のダメージを与えたのかがゲージで可視化される。アタッカー職は総じて高めだが,そればかりに注目してしまうとモンスターからタコ殴りにされ,これに起因するすったもんだは昔のMMORPGでは頻繁に見かけていた
 |
マジックアイテムのプロパティはランダムで付与される。高性能なユニークアイテムを1個獲得するだけでダメージレートが倍になることもあり,トレハンがめっちゃ熱い
 |
マジックアイテムがキャラクターにバインドされずに譲渡できるのは嬉しい仕様だ。ユニークアイテム(文字色が紫)とセットアイテム(文字色は緑)は,トレードや別キャラで使うことがあるかもしれないので「銀行」に保管しておこう
 |
外国人プレイヤーとのコミュニケーションに抵抗を感じる人もいるだろうが,難しく考える必要はない。最初は,「LFG Lv1 Warrior」とでも言っておけば,誰かから無言でinviteが来るかもしれない(※LFGはLooking for Groupの略。パーティへの参加を希望します,の意)
 |
こういった,昔ながらのオンラインゲームの香りを残した作品が,アーリーアクセスの段階で日本語にローカライズされたことは格別だ。ちなみに現在のSteamの売上ランキングでも,本作はかなりの上位に位置している
 |














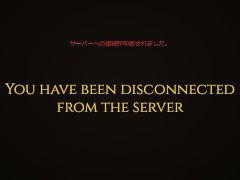






 Nevergrind Online
Nevergrind Online