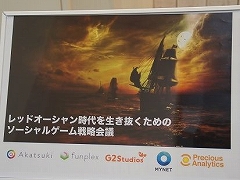イベント
開発で優先されるべきは論理か感性か。第1回「レッドオーシャン時代を生き抜くためのソーシャルゲーム戦略会議」をレポート
 |
本セミナーは,会社の垣根を超えたクリエイター同士が実情を語り,互いの認識をすり合わせつつ開発技術を相互に高め合うのが目的となっている。壇上にはソーシャルゲームの制作に関わる企業の代表者が招かれ,いくつかのテーマをもとにディスカッションが行われた。
 |
セミナーの開始にあたって,まずは主催であるPrecious Analyticsの代表取締役CEO,米元広樹氏が登壇。米元氏は「あまり議論が行われてこなかった情報を共有し,ゲーム業界全体がより良いプロダクトを生み出せるよう,この会を開催させていただきました」と,本セミナーの開催意図を語った。
主催のPrecious Analyticsは,データ分析や各種のシミュレーションを軸に,ソーシャルゲーム全般のゲームデザインに関するコンサルティングを行っている企業だ。
コンサルティングを行う側としては,企業側のスキル向上は都合が良く,クリエイター側としても外部のノウハウが吸収できる機会は貴重だ。ゲームアプリ開発や運営を行うG2 Studiosや登壇企業の利害が一致し,ポジティブなサイクルのもとで生まれた共同主催イベントだと言えるだろう。
 |
ディスカッションを行う登壇者は,アカツキのモバイルゲーム事業部で「八月のシンデレラナイン」プロジェクトリーダーを務める佐藤恵斗氏と,ファンプレックスのスタートアップ部ディレクターである石田達也氏,G2 Studiosシニアディレクターの石井真人氏,マイネットGS事業部プランナーの鷲頭加津麻氏に,米元氏を加えた5名だ。
 |
 |
 |
 |
第1回となる今回のテーマは「企画は感覚?ロジカル?徹底討論!」というもの。各登壇者が事前に回答した,テーマに沿った質問の内容に基づいて,議論が交わされる形となった。
●質問1:感覚を十分に発揮するべきポイント
最初にマイクを受け取った佐藤氏は,感性が重要になる工程として「施策や企画の具体案(Howの部分)」を挙げた。運営を続けるに当たって発生する問題の要因追求は論理によって導かれるが,解法は無数に存在する。そこから正しい答えを選び出すには感性に頼る部分が生まれる,というのが佐藤氏の主張だ。
続く石井氏も「可能な限り論理的判断を優先すべき」と前置きしつつ,課題解決や新たな遊びの実装にあたって「それがなぜ面白いのか」といった検討を行うに当たっては,ロジックを切り捨てて感性を優先する場合もあると語る。
いずれの登壇者も,論理で解決可能な部分はそれを適用し,明瞭な理由を組み上げるのが構造的・時間的に難しい場合に感性に頼る,という方向性に違いはないようだ。
なお,ここでは言語化が難しい特殊なロジックの発露としての“勘所”を感性と呼んでいる部分が多く,単なる当て推量ではない点には注意が必要だろう。
 |
●質問2:ロジカルに考えるべきポイント
こちらに関しては「工数の削減」や「問題原因の追求」といった,直線的でゴールが見えている(最終的にどうなれば良いかが分かる)問題については論理的な思考が適用可能である,という考え方が大方の同意を集めていた。
鷲頭氏は,その中でも特に「優先順位の決定」には明確な理由(ロジック)を用意する必要があるという。実働部隊に次の業務を説明するにあたり,可能な限り相手に納得感のある業務を与える事を重要視しているようだ。
それに補足する形で,石井氏は「優先度が低い意見も否定せず,課題として残しておくのも大切です」とコメント。スケジュール上の問題ですべてに対応するのが不可能であったとしても,行われた問題提起を正しく認識することが,今後の改善に繋がるという事だろう。
ゲームバランスの話題が挙がった際は,やはり論理的に組み上げるべきという意見が大勢を占めた。それに補足する形で,石田氏は「論理的に組み上げた後,実プレイによるチェックは必須」と語る。数値上のバランスが正しく機能していたとしても,その実装形態によって体感が異なるというのだ。
それに佐藤氏も賛同し,例えば,1000個収集せねばならないドロップアイテムを実装するとして「特定クエストを周回して1000個収集で達成」と「額面上必要な個数を1万に設定し,ログインボーナスで9000個配布。実際に収集する数は1000個」とした場合では,実数は同様でも体感は変化すると話す。そうした部分を導くには,やはり“感性”の助けが必要になるようだ。
●質問3:線引きが難しいポイント
どちらの側面を優先するか悩む部分としては,石田氏が取り上げた「何らかの習慣を壊す時」という回答に話題が集まった。
ここで言う“習慣”は組織内部のシステムなどだけではなく,ゲームシステム上で定着した概念やルールの事だ。ディスカッションの中では「論理的に見て明らかに変更すべきである事は分かっているが,現在の形に慣れ親しんでいるファンも多いUI等の改修」が例として挙げられている。
慣れや習慣に絡む要素は,惰性で行っているように見える施策であっても,それをカットする事でゲーム自体のクローズにつながってしまう例もあるという。こうした問題については,ユーザーから受け取った意見を正しく分析し,時には決断的に動く必要もあるようだ。
また,開発において個人個人に向けて仕事内容を説明する際は,相手に合わせて論理型・感覚型の説明を切り替える必要があると,鷲頭氏は語る。
先程は優先順位の説明にはロジックが必要だと話していたが,相手の性質が分かっているのであればそちらに合わせる事を優先するそうだ。こうした考え方は,チーム全体の開発モチベーション向上にも繋がり,結果的にアウトプットの質の向上に繋がるという。
 |
こうしたディスカッションを経て,今回のセミナー「レッドオーシャン時代を生き抜くためのソーシャルゲーム戦略会議」は終幕となった。本セミナーは定期的に開催を予定しており,共催・協賛企業や会場・規模・テーマなどを変えながら,今後は内部数値や専門技術の運用等についても触れていく予定だという。興味がある人は参加を検討してみよう。
 |
「レッドオーシャン時代を生き抜くためのソーシャルゲーム戦略会議」イベント情報
- この記事のURL: