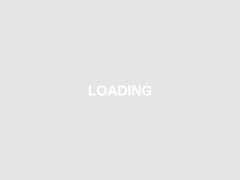連載
Access Accepted第847回:海外ゲーム通ならプレイしておくべき2025年のタイトル10選
 |
2025年も残りわずかとなり,海外ゲーム業界における動向を解説する当連載も,この記事で年内最後の掲載だ。というわけで,筆者がプレイした海外ゲームタイトルの中から,今年を象徴すると思われる10作を紹介する。単純に面白かった作品ではなく,今の情勢や今後のトレンドにつながるような作品を中心に選別している。まだ遊んでいないタイトルがあれば,今後のゲーム市場を読み解くためにも遊んでおくべき作品群だ。
2025年のゲーム市場のトレンドを総括
2025年は,ゲーム業界にとってはニュースに事欠かない1年になった。3月にはヨーロッパ最大手のパブリッシャであるUbisoft Entertainmentを巡り,中国の雄Tencentが創業家関連の新設会社へ出資を行う形での連携強化が決定。これにより経営基盤の盤石化を図ることになった。また,9月末にはアメリカ最大手であるElectronic Artsがサウジアラビアの政府系ファンドを中心とするコンソーシアムによる約550億ドルの買収提案に合意。取引は2027年度第1四半期に完了予定で,完了後は非公開企業となる見込みだ。また,今年最も注目されていた「グランド・セフト・オートVI」の発売が2026年11月16日に持ち越されたのも,ゲーム産業にとってはただならぬ影響を与えた出来事だろう。
Ubisoft EntertainmentとElectronic Artsといえば,どちらにとってもフラグシップタイトルである「アサシンクリード シャドウズ」と「バトルフィールド 6」がリリースされている。「アサシンクリード シャドウズ」が巻き起こしてきたアート盗作疑惑を始めとする “弥助問題” も大きなトピックだった。ゲームプレイとしては四季や天候によってプレイ状況も変容するシリーズの目新しさもあったが,最終リリース版では「日本を舞台にした大航海時代の奴隷問題」というテーマだったはずの弥助の物語が大幅に削られていた。そのため,アサシンではない彼が主人公である意味を問わざるを得ない仕上がりだ。
 |
アート盗作疑惑に関しては,Sony Interactive Entertainment傘下にあるBungieも例外ではない。年内のリリースが予定されていた「Marathon」が,公式発表では開発状況や品質確保を理由に2026年への延期が決定している。「スロップの時代」(Slop Era)という不名誉なバズワードも耳にする昨今,生成AIで “それらしい” アートがいとも簡単に量産されてしまうからこそ,逆にアートディレクターの作家性と真価が問われているといえる。
圧倒的な独自の世界観を持つ「Clair Obscur: Expedition 33」や,手描きの緻密さが光る「Hollow Knight: Silksong」が高い評価を得ているのは,そうした「安易な生成」への反動にほかならない。
ゲーム市場の動向で言えば,「Marathon」に見られるようにプラットフォームホルダーは独占に固執せず,相互リリースする立場を強めている。特にXbox陣営においてそれが顕著だ。
ハードウェア市場に目を向けると,Nintendo Switch 2がローンチされる一方で,PlayStation 5とXbox Series X|Sは部品高騰により値上げを敢行。アナウンスされたばかりの新型「Steam Machine」も,2026年初頭のリリースを予定しながら価格帯は未発表のままだ。
こうしたコスト増の波はソフトウェアにも押し寄せており,AAAタイトルの1本80ドルは当たり前,いよいよ100ドルになるかという議論も当連載で紹介したとおりである。
 |
リサーチ企業Circanaの報告によると,アメリカのゲーマーの60%以上は新作ゲームを年に2本程度しか購入しないという。
その背景には,F2P(基本プレイ無料)型タイトルの定着や,運営型ゲームによるロングテール化が決定的要因として挙げられる。加えて前述した価格の高騰も重なり,新作が極めて売れにくい土壌が出来上がっているのだ。こうした市場構造の変化が,中長期的に産業へ暗い影を落とすのではないか──。そう危惧せざるを得ない1年だった。
コロナ禍を経て,筆者の取材範囲はシンガポール,ノルウェー,ブラジル,スペインと,これまで未踏だった地域へと広がった。そこで目の当たりにしたのは,国を挙げてゲーム産業の育成に邁進する各国の熱気だ。
正直なところ,数日の強行軍でも帰国後2週間は時差ボケを引きずってしまう。だが,身体的な負担を推してでも伝えたい「未知の良作」が世界には山ほどある。その使命感こそが筆者の原動力だ。
前置きはこのくらいにして,当連載の年末恒例企画「海外ゲーム通ならプレイしておくべきタイトル10選」をお届けしよう。選出基準は単純な面白さやセールス記録ではない。市場の「今」を象徴しているか,あるいは新たな表現やスタイルを確立しているか。その点に尽きる。もちろん,すべての人に共感してもらえないのは承知しているが,未プレイの作品があれば,ぜひ年末年始のライブラリに加えてみてほしい。
 |
キングダムカム・デリバランスII
開発元:Warhorse Studios発売元:Deep Silver
2018年にリリースされた「キングダムカム・デリバランス」は,“ドラゴンも魔法もない中世ファンタジー” として注目を集め,中央ヨーロッパの歴史に焦点を当てたストーリーやゲーム性が高く評価された作品だ。その新作である「キングダムカム・デリバランスII」(PC / PS5 / Xbox Series X|S)も,15世紀初頭のボヘミア王国を現実的に表現している。ボヘミア王国と神聖ローマ帝国の戦いが激化していくなか,主人公ヘンリーが両親の仇を討つための壮大な冒険を追い,プレイヤーの決断によって悪人になるのか,善人として敬われることになるのかの結末が決まっていく。
 |
「キングダムカム・デリバランスII」は,前作同様にシステム重視のゲームデザインながらもしっかりと1作の長編ゲームとしてまとめ上げるのに成功した。ヘンリーは食事や睡眠を摂らないと活力を失って失神してしまうこともあるし,食べ過ぎもスタミナが減ってゲームプレイに悪影響を与える。体力を向上させず,重い鎧を着ていては動きが鈍るうえ,戦闘もプレイヤーの経験とスキルの向上を要求しつつ,フラストレーションが溜まらない程度にプレイを楽しんでいける。テンポの良いストーリー,UI,評判システム,そしてグラフィックスや音楽も,確実に前作を大きく超えた作品だ。
RV There Yet?
開発元:Nuggets Entertainment発売元:Nuggets Entertainment
今年は「Co-opゲーム」が豊作の1年だった。このジャンルを代表するHazelight Studiosによる「Split Fiction」を筆頭として,親子でも一緒に楽しめる「LEGO Voyagers」,協力して山登りする「PEAK」,清掃作業をこなす「PowerWash Simulator 2」が,戦闘を重視しないタイプのCo-op専用ゲームとしてリリースされた。
だが,ここで選んでおきたいのは「RV There Yet?」である。おじさん4人組がキャンプから帰宅するため,とてつもない悪路が続く山道を乗り越えていくというだけの,ユーモアたっぷりないわゆる“ドタバタ系”だ。実質的に複数のプレイヤーが参加しなければキャンピングカーを前に進ませられないなど,協力プレイが不可欠なシステムに落とし込まれている。
 |
「RV There Yet?」が特異なのはインディータイトルなのにもかかわらず,初週の同時アクセス者数10万人越えを記録し,現在までに450万本ものスマッシュヒットになったということだろう。しかもバグも多いしパフォーマンスの最適化に問題があったにもかかわらず,ゲーマーはそれに目を瞑ってSteamレビューでは「圧倒的に好評」を与えている。つまり,「ゲーム体験の良さ」がネガティブポイントを上回っていることの証左だ。
Hades II
開発元:Supergiant Games発売元:Supergiant Games
2024年4月からアーリーアクセス版がリリースされていたので,なんとなく2025年のゲームという気はしないが,常にインディーシーンをけん引してきたSupergiant Gamesにとっては初の続編ゲームとなる「Hades II」(PC / Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch)。本作はローグライク・ダンジョンアドベンチャーとして完成度が非常に高く,出張が多い1年だった筆者にとって,飛行機の中での良い旅の友になってくれた。
 |
正統な続編である「Hades II」は,前作の核であった「オリュンポスの神々の祝福」というシステムを継承しつつ,新たに「魔術」を主軸に据えることでプレイフィールを刷新した。 打倒クロノスを掲げる主人公メリノエは,伝説の武具と古の魔術を駆使し,そこに12柱を超える神々の功徳(Boon)を掛け合わせる。これにより,ほぼ無限とも言えるビルド構築が可能となった。大幅に拡張された世界観に加え,ソウルライクな緊張感を漂わせるボス戦,そして50時間を超える濃密な物語は,本作が単なる「追加要素の入った続編」の枠に留まらないことを証明している。
Blue Prince
開発元:Dogubomb発売元:Raw Fury
「Blue Prince」(PC / PS5 / Xbox Series X|S)は,ミステリーとストラテジーが融合した,類を見ないパズルアドベンチャーだ。叔父の遺産を継ぐため,ホリィ山麓の邸宅を訪れた主人公。彼(プレイヤー)に課されたのは,さまざまな機能を持つ部屋のタイルを選び,「45室の間取り」を建築しながら,幻の「46番目の部屋」へと辿り着くことである。
 |
各部屋は扉の方向が決まっているうえ,進行には鍵やコイン(歩数コスト)といったリソース管理が必須となる。さらに,日が昇れば設計図のアップグレード以外はすべて白紙に戻るというローグライク構造が,緊張感を生んでいるのだ。
また,部屋に残された痕跡からは,児童文学作家の失踪や政治的陰謀といった不穏な物語が浮かび上がる。単なるパズルに留まらず,ナラティブ要素が密接に絡み合っている点は見事というほかない。元ハリウッドの映像クリエイターがパンデミックを機に開発したという経緯も納得の,異視点から構築された作品だ。
Escape from Tarkov
開発元:Battlestate Games発売元:Battlestate Games
8年に及ぶベータ期間を経て,エクストラクションシューターというサブジャンルを打ち立てた「Escape from Tarkov」が,今年ついに正式ローンチを迎えた。いまや「バトルロイヤルの次」として,タクティカルシューター界で一大勢力を築き上げた同ジャンルだが,皮肉にもその立役者である本作の雲行きは怪しい。
 |
かつては硬派な難度とガンプレイで崇拝されたが,2024年に発表した250ドルもの高額エディションが「Pay-to-Win」であると猛批判を浴び,その名声に泥を塗ってしまったからだ。さらに11月のフルローンチに際しても,既存プレイヤーへのSteamキー配布が見送られるなど,マネタイズや運営姿勢への不信感は根強い。ジャンルの開拓者として,評価を覆すことができるのか。その真価が問われるのはこれからだ。
ARC Raiders
開発元:Embark Studios発売元:ネクソン
元EA DICEのパトリック・ソダーランド(Patrick Soderlund)氏らが関わるスウェーデンのEmbark Studiosがローンチしたばかりの「ARC Raiders」(PC / PS5 / Xbox Series X|S)も,上記の「Escape from Tarkov」からの系統に属するエクストラクションシューターだ。こちらは10月30日のローンチ以降,770万本の大ヒットになり,同時アクセス者数はピーク時70万人に達するほどの活況を帯びている。
「ARC Raiders」は,殺伐としがちなこのジャンルに「信頼」という概念を持ち込んだ点が新しい。その根幹にあるのは,脅威である「アーク」があまりに強靭であり,ほかのプレイヤーと争うよりも共闘したほうが生存率が上がるというゲームバランスだ。
システム面でも“Don’t Shoot”(撃つな)というエモートが実装されている点が象徴的だろう。これらが緩衝材となり,疑心暗鬼な戦場において「引き金を引かない」という選択肢と,安堵感のある協力関係を生み出している。
 |
本作は,敵の行動に機械学習を,NPCには生成AIを能動的に導入した点でも,2025年を象徴するタイトルだ。アメリカでは声優組合のストライキによりAI規制の動きが強まったが,スウェーデンのデベロッパである彼らは,技術による効率化と表現の拡張を迷わず選んだのだろう。アメリカの規制だけでこのグローバルな潮流をせき止めることは不可能であり,本作の成功は,AIと共存する未来が不可避であることを示す道標となったといえるのではないだろうか。
The Alters
開発元:11 bit studios発売元:11 bit studios
「The Alters」(PC / PS5 / Xbox Series X|S)は,謎の惑星に墜落した宇宙船の唯一の生存者である修理工ヤン・ドルスキーが,過酷な環境を生き抜くために自分自身の複製“オルター”を作り出していくSFサバイバルだ。基地運営や資源管理を行うシミュレーションとしての側面に加え,本作には強烈な“ひねり”が加えられている。
生成されるオルターたちは,単なるクローンではない。「過去の特定の時点で,異なる選択をした自分」なのだ。植物学者や鉱山労働者といった専門スキルを持つ彼らは,異なる人生を歩んだがゆえに,オリジナルとは別の人格を有している。つまりヤンは,選ばなかった可能性としての自分自身と向き合い,共同生活を営まなければならない。
 |
物語が進むにつれ,倫理的なジレンマを伴う決断が次々と迫られる。「This War of Mine」や「Frostpunk」を手掛けた11 bit studiosらしく,インタラクティブな手法でヒューマニズムを問いかける手腕は流石だ。「もし,あの時に別の選択をしていたら?」──誰もが一度は抱く普遍的な問いを,ゲームシステムに見事に昇華させた意欲作である。
HORSES
開発元:Santa Ragione発売元:Santa Ragione
「HORSES」の顛末については,本誌ニュース記事で紹介しているので繰り返さないが,イタリアのインディーデベロッパSanta Ragioneが作り出した本作は,サマージョブを紹介されて田舎の農場にやってきた主人公のアンセルモが,馬の世話を申し付けられるというゲームだ。しかし,その馬たちはウマではなく,馬のお面を被せられて洗脳された人間たちだったというホラー的なストーリーを,1920年代の無声アヴァンギャルド映画のようなモノクロで描いている。
 |
開発元にとって最大の不運は,反対派からの抗議を受けたSteamとEpic Gamesが,発売直前になって販売禁止処分を下したことだろう。 表向きの理由は,当初の査定である「17歳以上対象(Mature)」に対し,実態が「18歳未満禁止(Adults Only)」に相当するというものだった。だが,作中の過激なシーンには徹底したモザイク処理が施されている。馬のマスクを被った裸体を「猥褻」とみなすか,アヴァンギャルドな「芸術」と捉えるか。その境界線は判然とせず,本作の騒動はゲームにおける表現規制の在り方に,改めて一石を投じることとなった。
Hollow Knight: Silksong
開発元:Team Cherry発売元:Team Cherry
「Ghost of Yōtei」から「バトルフィールド 6」,そして今回の連載記事でも「キングダムカム・デリバランス II」や「Hades II」のように,“前作を超えてきた” 続編が豊かだったのも2025年の傾向だったが,Team Cherryによるメトロイドヴァニア「Hollow Knight: Silksong」(PC / PS5 / Xbox Series X|S / Nintendo Switch 2 / Xbox One / Nintendo Switch)もその1つだ。不気味さと可愛らしさが混在するムシたちの王国という設定の,描き込まれた背景のビジュアルが印象的で,さらに難度が高くなったゲームプレイが,その風貌に相反するかのようにプレイヤーにチャレンジを与える。
 |
最大の変化は戦闘だ。地に足のついた堅実な操作感が特徴だった前作に対し,本作はスピードと上下移動を意識したアクロバティックなものへと変貌を遂げた。空中での回復も可能となり,そのプレイフィールはまるでダンスを踊っているかのように軽やかだ。
システム面では,チャームが「クレスト」や「ツール」へと刷新され,プレイスタイルに合わせたビルド構築の自由度が大幅に向上している。一方で,その先鋭化した難度がアクセシビリティの低下を招いているという指摘は否めない。だがそれは,「続編はいかにあるべきか」というゲームデザインの根本的な問いを,我々に突きつけているようでもある。
Clair Obscur: Expedition 33
開発元:Sandfall Interactive発売元:Kepler Interactive
良作揃いの2025年だったが,終わってみればThe Game Awards 2025は「Clair Obscur: Expedition 33」(PC / PS5 / Xbox Series X|S)の独壇場だった。9部門制覇という圧倒的な結果は,本作が今年の顔であることを何よりも雄弁に物語っている。
人類を滅ぼす「ペイントレス」への特攻任務を描くClair Obscur: Expedition 33。その絶望的な旅路は,やがて家族の愛憎や芸術論へと深淵を広げていく。一筆が現実を塗り替え,運命すら書き換えてしまう世界で,プレイヤーは「生と死」,そして「芸術と現実」の狭間を彷徨うことになるのだ。
ベル・エポック期のフランスを想起させる退廃美,それを彩る楽曲,そして敵ターンでも緊張感が途切れない半リアルタイムバトル。そのすべてに職人芸が息づいている。
かつて海外市場において「JRPG」という言葉は,レトロ回帰を謳うインディゲームの “免罪符” として使われる側面もあった。だが本作は,そのステレオタイプを粉砕したといえる。伝統的なスタイルに現代的な解釈を加え,このジャンルが持つ表現と遊びの可能性を,改めて世界に知らしめた一作だ。
 |
The Game Awardsの壇上で,クリエイティブディレクターのGuillaume Broche氏が放った「坂口博信さんとファイナルファンタジーがなければ,今の僕たちはなかった」という言葉は,多くのゲーマーの胸を打った。本作は,JRPGというジャンルが国境を越えて継承され,独自の進化を遂げた証左だ。その熱量は,本家である日本のデベロッパにも「JRPGの新たな可能性」を突きつけたのではないだろうか。
また,授賞式で開発チームが着用していた赤いベレー帽も印象的だった。あれは単なるパフォーマンスではない。日本のサムライやヤクザ,あるいはポーランドのスラブ民話のように,自分たちのルーツである「フランス文化」を隠さず,むしろ最大の武器として世界に提示する。その潔さと「真正性(Authenticity)」こそが,本作を成功に導いた隠し味だったといえるだろう。
※次回の掲載は2026年1月12日を予定しています
※2025年12月22日20:55,初出時,Ubisoft EntertainmentとTencentの資本関係や,Electronic Artsの買収合意の進行状況について事実と異なる記載がありました。また,一部タイトルの記述において,著者の推測と事実の区別が曖昧な箇所がございました。読者の皆様ならびに関係各位にお詫び申し上げるとともに,該当箇所を訂正いたしました
- この記事のURL: