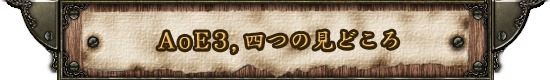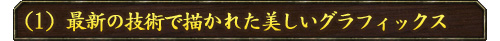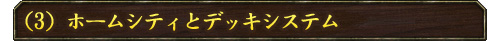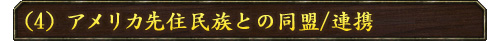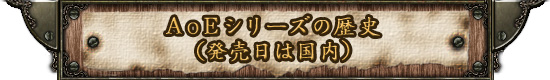度肝を抜くグラフィックスと前評判の高さから,RTSファンならずとも期待する新作「Age of Empires III」(以下,AoE3)。すでに10月18日に英語版は発売されたが,今冬に予定されている日本語版を待っているプレイヤーも多いことだろう。本連載では,日本語版発売に先駆けてAoE3の魅力を一から紹介していきたい。まず第1回では,AoE3の特徴と,その題材となる世界をざっと眺めてみよう。
なお本連載は,AoEファンはもちろん,RTSに詳しくない人にAoE3を通じてRTSに興味を持ってほしい,という意図も込めた記事作りを行っていくつもりだ。AoE3は決して初心者お断りの難解なゲームではないので,ぜひ本連載を通じてRTSの世界に飛び込んできてほしい。
AoE3は,どの国の歴史をテーマとしたゲームなのか? 前作と比べて,どこが新しくなったのか? まずは知っておきたい,AoE3の基礎知識を見てみよう。見どころは大きく分けて,以下の四つだ。
2005年1月にAoE3が発表された当初,一番の注目点はなんといってもそのグラフィックスの美しさにあった。あまりのクオリティに「これは本当にプレイ画面なんだろうか?」と疑問を持ってしまったほどだ。最新鋭のグラフィックスに目の肥えたFPSプレイヤーから見ると,相変わらず地味に見えるかもしれないが,RTSとしては破格の美しさである。
AoE3のグラフィックスでとくに優れているのが,光と影の表現だ。ゲーム内の時間はだいたい真昼前後に統一されており,ななめ上から降り注ぐ穏やかな太陽光が,なんともいえない心地よい雰囲気を出していて,限りなく自然に近い表現に成功している。水面の表現も秀逸で,海,川,湖それぞれの水の色の違いまで再現されている。
これまで最新のFPSなどには採用されていても,RTSではあまり活用されることのなかった,最新グラフィックス技術をぜいたくに取り入れて作られたのがAoE3だ。その意味で,AoE3はRTSのグラフィックレベルの新境地を開いたエポックメイキングな作品である。

AoE3は,15世紀〜19世紀のアメリカ大陸をめぐる,ヨーロッパ各国の抗争をテーマとしている。登場する勢力は,以下に紹介する8か国だ。
ゲームが始まるのは,15世紀末の大航海時代。コロンブスのアメリカ大陸到達を端緒に,この時代,ヨーロッパの列強は次々とアメリカ大陸に進出を開始した。先駆けとなったのは「スペイン」「ポルトガル」である。スペインは中南米へと進出,アステカ帝国やインカ帝国といった古代文明を征服し,莫大な富を得た。アジア,アフリカ方面へ進んでいたポルトガルもトルデシリャス条約を機にブラジルに足がかりをつかみ,植民地経営に乗り出した。
16世紀末ごろから,これら2国に代わって「イギリス」「フランス」「オランダ」の3国が台頭してくる。イギリス,フランスは絶対王政のもと,強力なリーダーシップで北アメリカへの植民を進めた。オランダはアムステルダムを中心に,世界の金融の中心地となって繁栄した。
やがてオランダは覇権を失うが,イギリスとフランスでは第二次英仏100年戦争ともいわれる,植民地と本国双方を舞台とする抗争が繰り広げられた。
AoE3にはこのほか,「ドイツ」「ロシア」「トルコ」の3国が登場する。これらの国は実質的にアメリカ大陸をめぐる戦いの歴史には登場しないものの,当時のヨーロッパで重要な存在感を示していた国々である。
ところで,この時代の戦争は二つの意味で過渡期であった。一つは剣/槍/弓矢中心から,火薬を使った戦闘への移行という意味。もう一つは,騎士階級や傭兵中心の戦争から,常備軍を基礎とする組織化された集団戦へと移り変わるという意味である。
また,経済発展の側面も見逃せない。18世紀にイギリスで始まった産業革命は,経済活動に機械や蒸気機関が導入されたことにより,社会のあり方を一変させた。貿易はますます盛んになるが,一方で自国経済圏の拡大は帝国主義へと繋がっていく。
AoE3は,このような歴史を背景として展開されていく。
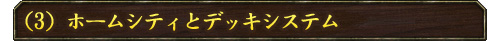
AoE3のゲームシステムの中心をなすものが,ホームシティ(Home City)だ。これは,ヨーロッパからはるばるアメリカ大陸へと植民活動に訪れているプレイヤーが,本国に対して救援の要請を行う,といったイメージのシステムである。
プレイヤーはゲーム中,探検・戦闘・生産・交易などを通じて経験値(XP)を獲得するが,このXPが一定量溜まるごとに,カードと呼ばれる本国への救援要請を行うことができる。カードには,物資を届けてもらうものはもちろん,兵士を呼ぶもの,特定のアップグレードを行うもの,建物に新機能を追加するものなど多種多様な種類があるが,どのカードを使うかはプレイヤー自身が選ぶ。
カードは各文明ごとに約100種類あるのだが,一回のプレイに使えるのはその中から20枚のみ。つまり,数多くのカードの中からプレイヤー自身が選択して20枚の「デッキ」を組んでプレイに臨むわけである。
デッキをどのように組むかによって生じる無限の戦略のバリエーションが,AoE3の最も面白い部分だ。例えば,兵士を呼ぶカードを多く使えば短時間で多くの兵士を揃えることが可能だし,内政のアップグレードのカードを使えば経済発展のスピードが加速するだろう。だが20枚という制限があるので,明確な狙いを持って選択し,関係ないものは捨てなければならない。
また一般的には,時代が進めば進むほど強いカードを使える。早い時代からどんどんカードを使っていって早期決着を目指すのか,長期戦にもちこんで後の時代の強いカードを使って優位に立つのかなど,デッキの組み方に対する興味は尽きない。対戦相手のデッキを見られので,とくにマルチプレイにおけるデッキの駆け引きはとても面白いものになっている。
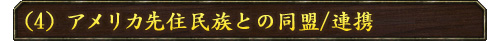
史実を振り返ってみると,アメリカ先住民族とヨーロッパ人は常に敵対していたわけではなかった。とくに北米においては,両者の積極的な貿易や,同盟を組んでほかのヨーロッパ諸国に対して共同戦線を張るといったことは珍しくなかった。
AoE3では,先住民族は戦う対象ではなく,味方にして共に戦う仲間という位置づけになっている。マップ上に存在する先住民族の集落に交易所(Trading Post)を建てることで,その先住民族固有の軍事ユニットを育成できるほか,先住民族固有のテクノロジー研究もできるようになる。これらはどれもヨーロッパの文明にはない特徴を備えているため,うまく利用すればかなりの価値がある。
プレイヤーの担当するヨーロッパ文明に,サブ文明ともいえる先住民族をどうやって連携させていくか。AoE3のもう一つのポイントといえるだろう。
全世界でシリーズ累計1600万本を売り上げたというAoEシリーズ(正確にはAgeシリーズと呼ぶべきか)。AoE3の発売により,今後もこの数字はどんどん伸び続けていくだろう。その輝かしい歴史を簡単に振り返っておきたい。
「エイジ オブ エンパイア」(Age of Empires,AoE)
1997年12月19日発売
記念すべき第1作。無論,RTSは本作の登場以前にも存在したが,とりわけ日本ではこのAoE1がRTSというジャンルを確立した最初の作品といっていいだろう。ストラテジーといえばターン制が当たり前だと思っていた頃,この作品を目の当たりにして,相当衝撃を受けたのを今でも鮮明に覚えている。
ゲームの舞台は古代で,石器時代から鉄器時代までの人類の曙をテーマとしていた。エジプト,バビロニア,大和など12文明が登場。拡張パックの「ライズ オブ ローマ」(Rise of Rome,RoR)では,ローマなど四つの文明が追加され,新ユニットも多数追加された。
「エイジ オブ エンパイア II:エイジ オブ キング」(Age of Empires II: The Age of Kings,AoK)
1999年11月26日発売
第2作の舞台は中世。本作も史実をテーマとしており,フランク,サラセン,日本など13文明が登場。外交,交易,固有テクノロジーなど前作から進化した部分は多数あったが,中でもゲーム性に大きな影響を与えたのが「ユニットが建物内に駐留できる」ようになった点であった。これにより攻守のバランスが大いに改良され,プレイにより深みが出た。
そのゲームバランスは拡張パック「覇者たちの光陰」(The Conquerors,AoC)において完成の域に達し,ファンの間ではAoCがシリーズ最高傑作であるとの呼び声も高い。
「エイジ オブ ミソロジー」(Age of Mythology,AOM)
2002年12月13日発売
前2作から大きく趣向が変わり,神話世界をテーマとした作品で,シリーズ中では外伝的位置づけをされることもある。大別して「ギリシア」「エジプト」「北欧」の3種の文明があり,実際の神話をモチーフにした幻獣や英雄が多数登場,個性ある戦いを繰り広げるのが楽しい作品であった。ゴッドパワーと呼ばれる,一瞬にしてプレイの形勢を逆転させかねない必殺技のようなものが行使できる点も,ゲーム性に大きな影響を与えた。
拡張パック「アトランティスの巨神たち」(The Titans)ではタイタンと呼ばれる,ゲームの最終段階で登場する超巨大ユニットが追加。より派手な戦いが楽しめる。